石橋優介(一級建築士)
最新記事 by 石橋優介(一級建築士) (全て見る)
- 【1,000万円は可能?】建築士の給料は安い?独立開業した一級建築士が解説! - 2020年7月7日
- 一級建築士の難易度は?現役資格学校講師が教える合格の勉強時間の目安や最短合格法!! - 2020年6月16日
- 建築士の受験資格を通信で取得!建築士が教える最短ルートはコレ - 2020年5月25日

激務、薄給等のイメージが強い建築士。
そして、建築士を目指す方が気になるものの一つが給与事情。
個人設計事務所、組織設計事務所、独立開業を経験した私が、経験を踏まえながら仕事とお金の話をご説明いたします。
この記事を読むメリット
- 建築士の給料についてリアルな事情が分かる
- 個人設計事務所、組織設計事務所、独立開業など実際の体験が分かる
- 建築士の試験に合格するためのおすすめの通信講座が分かる

建築士の給料は資格によって変わる


就職や転職時に多くの方が気になる項目は、業務内容・報酬(給与や諸手当)・待遇です。
手当で差がつく
多くのハウスメーカー・ゼネコン・設計事務所では、資格の保有による基本給は概ね大きくは変わりませんが、諸手当で大きく差が付きます。
最近の建築系の会社では、資格手当を手厚くしている傾向があります。
これは、会社としても資格保有者の数を増やしたいということなのでしょう。
木造建築士
木造建築士は、2階以下の小規模の木造の設計・監理ができる資格です。
私の経験上又は知っている上では、木造建築士を所有していることで、建築士の資格がないよりは就職・転職時に優位ではあることには変わりはないと思いますが、会社として特別な手当を出しているところはあまり見たことはありません。
木造建築士はほぼ無い
基本的には、二級建築士へのステップアップの資格としての位置づけが大きいので、木造建築士の資格手当はないものとして考えてよいでしょう。
二級建築士
二級建築士は、概ね3階以下の住宅規模の建物を設計・監理することができます。
二級建築士の手当
上記の業務が中心となるハウスメーカーや設計事務所においては、平均で月3000円~5000円程度の支給額ではないでしょうか。
しかし、就職・転職時に二級建築士を所有していると優位になりやすいと考えられます。
ただし、組織設計事務所への就職・転職時には、あまり優遇はされません。
組織設計事務所では、大規模木造、S造、RC造等の比較的規模が大きい建築を設計することが多く、一級建築士を持っていることが採用の条件であることが多いです。
大手~中堅の組織設計事務所では、スタッフ育成の上でも二級建築士を所有していると一級建築士への受験がしやすいため(試験の経験上)、20台であれば積極的に採用を行っているのではないでしょうか。
一級建築士
建築士の最上位である一級建築士は、設計・監理ができる建築物に制約が無いため、多様な建築物を設計する組織設計事務所やゼネコンで非常に重宝されます。
一級建築士の手当
資格手当としては、月5000円から20000円程度の支給額です。
一級建築士を所有していることで、基本給が大きく上がるかといわれると会社によって異なるとしか言えませんが、官庁の物件では主任技術者以上の体制上の立場に就くことができ、業務の中心的な存在となります。
また、官庁発注のプロポーザルでは、一級建築士の在籍人数や経験年数も加点のポイントとなり得るため、非常に重宝される資格であることには変わりありません。
より上位の建築士を目指す方は、以下の通信講座又は受験対策講座をオススメします。
スタディング/ https://studying.jp/
総合資格学院/ https://www.shikaku.co.jp/
日建学院/ https://www.ksknet.co.jp/nikken/index.aspx
一般社団法人 全日本建築士会/ https://ssl.kenchikukouza.org/index.html
業界でも変わる建築士の給料・年収


世間一般では、建築士の報酬は薄給のイメージがついています。
これは、非常に長い勤務時間から想定されるものだと思います。
決められた勤務時間の中で、効率よい仕事をし、高い成果を残すことが求められる現代社会の中では、時代錯誤的な仕事なのかもしれません。
過労死やパワハラ等の社会的な企業の問題が明るみになり、多くの建築系の会社でも働き方改革が推進されています。
決められた時間の中(勤務時間内)で、クライアントの希望以上の成果を上げ、利益を生むことは確かにプロですが、建築はなかなかそうではないと思います。
建築士のリアル
決められた時間外(勤務時間外)でも、悩んで、検討して、失敗して、改善して、失敗して、、、を繰り返します。

よりかっこよく、より安全で、より安くを最後の最後まで追求します。
自分の専門分野外の人と関わり、とりまとめ、クライアントに説明し、納得してもらう仕事ですよね。
そして自分以外の調整する仕事が圧倒的に多すぎるため、どうしても決められた時間内(勤務時間内)には終えるポイントが見つかりにくい仕事です。
もちろん納期を守ることは必要ですが、納期内で最大限に時間を費やし成果品をつくります。
よって、よく時給に換算すると、、、のような話しがありますが、甚だ割に合いません。
ここからする話は、あくまで筆者の経験上の話なので、就職・転職をお考えの方はあくまで参考程度に捉えていただければと思います。
アトリエ系:ほぼ無給(年収:約100~300万円程度)
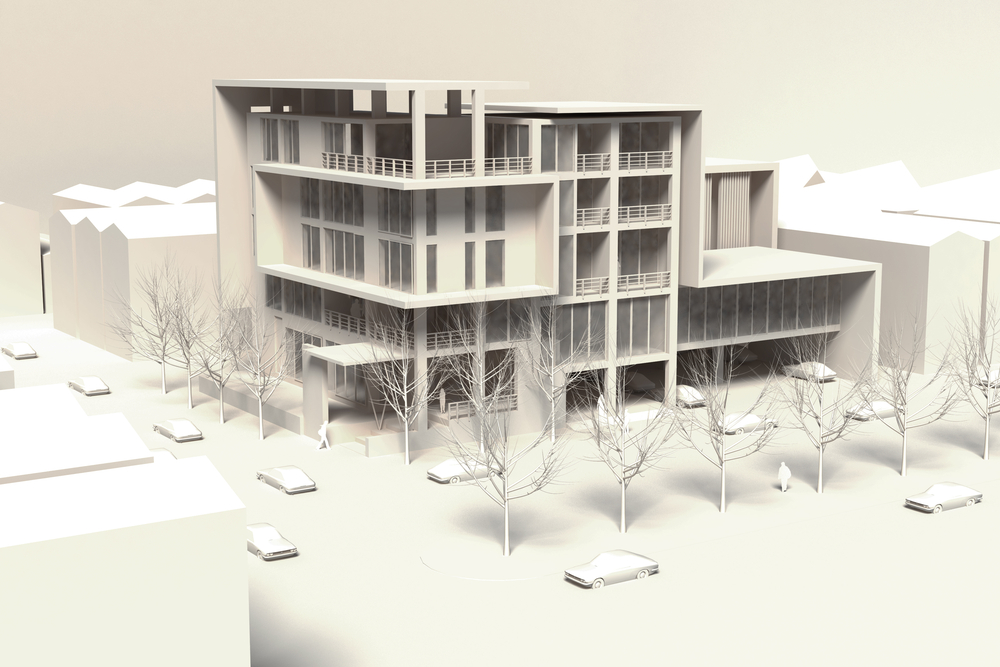
今はアトリエ系という言葉は死語かもしれませんが、所謂、有名な建築の先生の設計事務所や雑誌(新建築や日経アーキテクチャー等の専門誌)に多くでている個人設計事務所の事を指します。
学生や建築の仕事をして間もない若い頃には、アトリエ系の設計事務所で勤務することを夢見る方も多い(多かった)のではないでしょうか。
私は、大学生・大学院生時代に、どちらかというと学校の講義より設計事務所のアルバイトやオープンデスクに沢山参加していました。
今は普通にオープンデスクという言葉があり、社会にでる前に企業で勉強をさせてもらうというシステムがありますが、私が学生だった10数年前は、オープンデスクという言葉は無報酬の丁稚のようなイメージがあったと思います。

講義がない日や土日、夏休みを利用して、自分がカッコいいと思った事務所にメールを送りオープンデスクやアルバイトをさせていただいていました。
当時はオープンデスクでしたので、アトリエ系の事務所では当然無給でした(何も仕事に貢献できてませんでしたし、模型やCG制作の補助が殆どでした)
寝袋を持参して、泊まり込みでアトリエで仕事をさせてもらい、交通費を浮かしたこともありました。

アトリエの給料
多くのスタッフの方と出会いましたが、多くの報酬を貰っているイメージはありませんでした(だいたい10~15万円/月程度でしょうか、ボーナス等はないと思われます)
しかし、その事務所の先生の威厳に触れたり、事務所内の緊張感、華やかな仕事の裏にある気の遠くなるような検討作業等を体験し、非常によい経験でした。

私はオープンデスクで、模型製作のテクニックやCGのつくり方を学びました。
当時私はshadeというCGソフトを使っていましたが、たまたまオープンデスク先のスタッフの方もshadeを使っていて、驚くような美しいグラフィックを制作していたことを記憶しています。
shadeとphotoshopを駆使して、短時間に設計者の意図を明確に伝えるようなプレゼンテクニックをご教授いただきました。

苦労を買ってでも、苦労することが美学であったような時代だったのか、それに酔いしれていただけかは分かりませんが、お金は無いが時間と体力だけは有ったので経験できた事だと思います。
私が初めて就職したのは、地方の個人設計事務所でしたが、給料は月15万円程度でした。
何も仕事はできませんでしたし、仕事を教えていただき、学ばせてもらっているという立場でしたので、給料を頂ける事がありがたいとすら思っていました。
当時は、確認申請すら一人でできませんでしたし、図面の書き方も全く分かっていませんでした。
当時の指導していただいた方が、根気よく図面に赤チェックをつけてくださり、建築士の見習いとして育てていただきました。
アトリエのメリット
個人事務所(アトリエ事務所を含む)に勤めるメリットとしては、大きな組織事務所等と比較すると一案件に注力しやすい環境にあることです。
時間や成果品の対価としての報酬はなかなか求め辛いですが、将来へのステップアップのために、経験を積むという点においては、就職や転職の選択肢の一つにしてもいいのではないでしょうか。
しかし、最近の有名な個人設計事務所程、給与(月給やボーナス)が月20~30万円程度と安定し、良好な作業環境のもと、制作活動を行えるようになってきています。

お金はありませんでしたが、多くの技術を学び、建築の実務の現場を体験できたことは、社会にでるまでの糧となりました。
地方組織設計:年収約350~500万円

地方の中堅~大手の組織設計事務所(他地域に支店・事業所をもたない会社)では、月25~30万円(総支給)程度ではないでしょうか(手取りにすると20万円~25万円/月程度)
地方組織設計事務所の特色としては、官庁と民間の業務の比が6:4や7:3程度であり、入札やコンペ・プロポーザルで仕事を受注している形態が多いと考えられます。
官庁案件はボーナスもある
会社の規模にも因りますが、官庁案件が継続して多い事務所は、比較的給与も安定して多くボーナスもあると考えられます。
私が個人設計事務所の次に勤めたのが、地方の組織設計事務所でした。

地方の官庁案件が中心であり、改修から新築までの多くの業務を経験することが出来ました。
組織設計事務所という一つの社会が初めて体験するものであったので、チームで業務を進め、スタッフ一人が複数案件を抱えるというスタイルがとても新鮮でした。
チームで設計することの難しさと楽しさを学びました。
この頃は特に、自分の収入に対して、不満や希望はありませんでした。
兎に角、仕事を覚えるのに必死でした。
大手組織設計:年収約450~800万円

全国各地に支店や事業所を有する大手の組織設計事務所では、月30~50万円(総支給)程度なのではないでしょうか(手取りにすると25~45万円/月程度)
大手組織設計事務所の特色としては、組織設計事務所毎に得意分野(特化した設計)があり、民間から官庁案件まで広く受注しているという点です。
大手組織設計の案件
この規模の設計事務所になると、木造2階建のような個人邸宅等の案件は少なく、どちらかというとS造やRC、SRC造、大規模木造建築の受注が多く、意匠・構造・設備(電気・機械)の各専門分野の設計者が協働して設計を進めていきます。
給与面だけではなく、社会的なステイタスも大きくなるため、より仕事に遣り甲斐が持てるのではないでしょうか。
私は現在、個人設計事務所として独立していますが、最後に勤めたのが大手組織設計事務所でした。
全国各地に支店があり、一級建築士をはじめとした技術者の人数も多く、複数の専門分野の設計チームによって案件を進めていきました。
設計する規模が大きくなるにつれて、遣り甲斐は大きくなってきましたが、勤務時間も大きく増えました。
報酬としては、一般的に言われる手取り=年齢以上の金額は頂いていましたが、勤務時間や責任が増大し、仕事とプライベートのバランスが取りにくくなったことも事実でした。
お金のために仕事をやるわけでもないし、プロだからこそ対価が欲しい、対価ってなんだろうと様々な業務と報酬の事で悩んだ時期でもありました。

大手組織設計のメリット
大きな組織設計事務所の大きなメリットは、不特定多数の人が利用する地図に残る大きな建築物の設計・監理に関われるという点です。
もちろん、規模が大きくなると一人では設計できないので、意匠・構造・設備の設計者や多岐にわたる業種の方々、官庁の複数の課と協働して設計を進めていきます。
また、事務所(会社)に蓄積するノウハウや助言等も取り入れ易く、広い視点で常に新しい設計に取り組むことができます。
大手組織設計のデメリット
デメリットとしては、複数人で設計する以上、納期から逆算した工程管理が非常に難しくなるという点です。一人で設計する時間よりも、他者と協議・検討する時間の方が長いかもしれません。
設計者の総合力を問われる仕事の一つと言えるのではないでしょうか。
報酬の面だけに焦点をあてると、大手の設計事務所に行くほど(例えば日経アーキテクチャーで売り上げ又は純利益が20位以内の会社)、報酬や待遇も手厚くなります。
日経アーキテクチャーで毎年公表される、「設計事務所売上ランキング」のTOP10にはいる会社では、年収は700~1000万円近くあると想定されています。
私の所属していた会社は、20位以内の会社でした。
年収はTOP10に入る会社程は頂いていませんでしたが、家族3人が普通に暮らせる程度は頂いていた記憶があります。
ハウスメーカー:年収約350~1000万円

CMで流れているような大手ハウスメーカーでは、設計職の課長クラスになると1000万円も可能とされています。
毎月の給与は中堅・大手組織設計事務所と大きく変わりはありませんが、賞与が手厚いのがハウスメーカーの特徴なのではないでしょうか(全てのメーカー様が該当するとは限りません)
ハウスメーカーのメリット
ハウスメーカーは低層の住居系の建築だけの設計と思われがちですが、大和ハウスさんや積水ハウスさんのような大手ハウスメーカーになると、商業建築や物流建築等も展開し、大規模な建築に関わることができます。
また、業務内容は設計・監理・積算・現場管理など多岐に亘り、就業ニーズも多様化しています。
よって、あらゆるジャンルで自分に合った業務の道を目指すことができます。
建材メーカー系:年収約350~600万円

建築士の設計業務の中で欠かせない存在が、建築材料や工法に特化したメーカーです。
どの材料の分野でも、世の中に3社見積がある以上(1社独占業務はほとんどないので)、例えば屋根の防水メーカーでも複数の会社があり、独自の商品があります。
中でも単価が高くシェア比が高いメーカー(例 外壁:ニチハやKMEW等)になればなるほど、売上高も大きいため社員一人当たりへの報酬も大きくなります。
また、建築材料の分野は、日進月歩の業界であり、社会ニーズに合致した新しい商品が常に求められる仕事でもあります。

ゼネコン系:年収約500~1000万円

建築士として一番報酬が多いのは、ゼネコンの設計職です。
一般的にゼネコンは施工を行う会社のイメージがありますが、多くのゼネコンでは自社に設計部を持ち、土木・建築工事を請負う体制があります(一部の業務又は過半以上を設計事務所に外注する業務もあります)
大手ゼネコンの年収
日本が誇るスーパーゼネコンと称されるTOP5の大林組、大成建設、清水建設、鹿島建設、竹中工務店の設計職の年収は1000万円以上とも言われています(課長クラス)
私は大学時代、就職を考えたとき、何故かゼネコン系への志望意欲はありませんでした。
多くの仕事をして経験を積み、個人事務所から組織設計を経て、今は独立して設計事務所を営んでいますが、心のどこかでゼネコンの設計部が知名度や給与面等でうらやましく思ったりもします(もちろん、ゼネコンの設計部の業務もものすごくハードだと思いますが)
独立開業:0~青天井
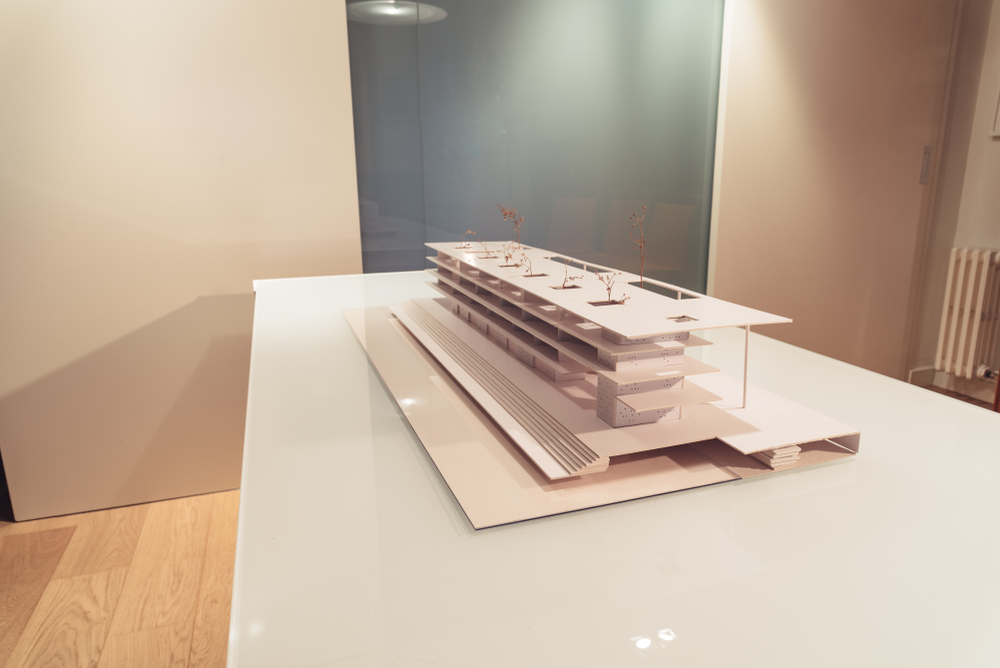
一級建築士事務所で開業すれば、設計できる範囲が広いため多くの設計機会(元請けから下請け)があります。

独立開業をして思うことは、元請けで設計・監理の仕事を頂くことは、とても難しいということです。
自分がクライアント様の立場になったとすると、何百万・何千万の仕事を任せるのに、世の中に石を投げたらあたるくらい会社があり、自分に任せらえる信用があるという点が一番ネックになります。
もちろん、デザインやコストマネジメントは独自のものがあり、みんな違ってみんないいの世界ですし、みんな腕がいいのは当たり前なので、最後はその人への信頼だと思います。
独立のポイント
これから独立を目指す方、将来的に独立したい方は、仕事を受けることができるコネクションを広くつくることが大切です。
仕事を受注するまでの比較検討の対象に入り込むことがまず大事です。
また、設計・監理以外の収入源を持っておくことも大切です。
建築士事務所を開業していると、資格学校の講師や講演・執筆の仕事などの収入を得る選択肢は多岐に亘ります
注意点
※建築士事務所に属していない建築士が、設計の業で報酬を受けると建築士法に抵触する恐れがあるので要注意してください
設計料は毎月決まった日に定額入ってくるとは限りません。
多いときも少ないときもあるので、受注状況が安定して軌道に乗るためには、資格を生かしてあらゆる収入源を増やす方法をストックしておく必要が絶対にあります。
今は私は、元請けの設計監理業の他に、資格学校の講師や執筆活動、CG作成、確認申請代行、下請けの設計業務等、幅広く事業を行っております。

建築士の給料が安いと言われる4つの原因


これまでにも述べましたように、建築の仕事(特に設計の仕事)は、設計以外の時間(お客様対応、協議等)がとりわけ長いため、労働時間(拘束時間)が長くなりがちです。
一般的なイメージとしては、建築士の給与は薄給と思われがちです。
実際のところ、建築士としてシッカリ稼いでいる人も多いですが、以下の理由が当てはまってきます。
【理由1】一級建築士ではない建築士は稼ぎにくいから
就職・転職の際に求められる条件で、「一級建築士優遇」というキーワードを見かけます。
企業としても、やは二級建築士よりは一級建築士の方を採用したいと思うのは当然です。
戦力になるかどうかの点では資格は関係ありませんが、仕事を受注する際、お客様との折衝の際には社会的責任が大きい一級建築士の方が信頼感や説得力はあります。
一級建築士の方が、企業により採用されやすいということです。
一級建築士が重宝される理由
よって、一級建築士の方が二級建築士や木造建築士に比べて、多くの職に就くチャンスが増えると同時に、設計可能な範囲も広いため、企業の立場からすれば重宝できるわけです。
また、二級建築士・木造建築士より一級建築士の方が資格手当も多いことから、報酬の面だけから考えると、一級建築士として勤務する方が、建築士としては稼げると思います。
逆に、二級建築士・木造建築士は、設計できる建物に制約があることから(二級建築士・木造建築士の業務範囲を参照)、就職・転職の際には、比較的小規模の建築物を設計・監理する業種に絞られてしまい、選択肢が少なくなってしまいます。
【理由2】残業が多い業界だから

働き方改革が謳われる昨今、「考えて働く」ということはどの業種にも共通して大切です。
納品に向けて、計画的に検討する時間・手を動かす時間を割り振り、成果品をまとめることは設計者として大切なスキルの一つです。
業界の現状
設計は妥協の産物とよく言われますが、検討や設計のどこかで落しどころをつくらないときりがないのが現実です。設計期間内に、納得いく設計やデザイン、コストマネジメントができる場合もありますし、どうしてもできないこともあります。
しかし、納期内にお客様のご要望以上の成果品を提供することがプロの仕事であるため、多くの設計者はプライベートの時間や睡眠時間を削ってでも仕事をしてしまいがちです(本当はあまりよくないことなのかもしれませんが。。。)
よって結果的に、どうしても残業が多くなってしまいます。

それは、設計が好きという気持ちと、(何かに)負けたくないという気持ちが体を動かしていたのだと思います。

若い頃は、「設計はお金じゃないよね、ハートだよね」と思っていた時もありますが、家族をもって、事務所を経営して、やはり対価の報酬は一番大切であると思うようになりました。
確かに設計職は残業は多いです。
しかし、建築士の資格を生かす仕事は、設計業だけではなく、前述したメーカー職や審査機関等多岐に亘ります。
人のライフスタイルは様々です。
時間内に仕事を終えて、しっかりプライベートを愉しみ、またキッチリ仕事をする方やその逆のスタイルに生きがいを持っている方も居られます。

そのような方程、時間に厳格で、細かい仕事をされているようにも思えます。
どの職種においても、できる限り残業が生じないような働き方や効率を向上させるための工程や手法の工夫はするべきですよね。
時給に換算したら、巷のアルバイトより低い…等とネガティブに思う/思われないような仕事をしたいですね。
【理由3】正しい設計料が、一般の方に知られていないから

お客様にとっての最終的な成果品は、安全で使い勝手が良くて、メンテナンスが容易な建築物そのものです。
もちろん建築士にとってもそれは変わりありませんが、設計の業務で考えると、成果品は設計図書になります。
一般的な住宅(30~50坪程度)でしたら、意匠図・構造図・設備図(電気・機械)を併せても50枚程度に納まりますが、構造計算が必要な建築物においては、設計図書は何百枚にもなったりします。
しかし、打合せ等でお客様が実際に目にする図面は、仕上表・配置図・平面図・立面図・断面図・展開図程度なのではないでしょうか?
設計図書を作成するのに、設計事務所は建築士法に基づいた報酬基準(国交省告示98号)に基づいて設計料を算出するのですが、お客様の立場からすると、これだけにそんなにもかかるの!!?と思われると思います。


建物に何千万も掛かるのは納得はされると思います。
しかし厚さ1~2センチ程度の設計図書に何十万から何百万も掛かってしまうのは何で??と思われるのはいささか仕方がないことでなのです。
最終の成果品は建築物
建築物を立てる過半は、一般の戸建てを求められているお客様であって、その方々に近いハウスメーカーや設計施工を業とする工務店の最終の成果品は建築物(戸建)であるからです。

お客様の立場からすると「家に〇〇〇〇万円掛かる」と「設計に〇〇〇万円、家に〇〇〇〇万円掛かる」と言われるのでは、え、設計料そんなにかかるの!!家とセットじゃないの?と思ってしまうのは至極普通のことなのです。
一般の方々は、設計料の相場を存じ上げないと思います。
それはハウスメーカーや工務店などの売り方が建物価格坪〇〇万円のような書き方であるからです(それが設計料を除いた金額であれば筆者も納得いきますが...)
ゆえに、市場では設計料って特別に掛からないイメージがあります。
しかし、いざハウスメーカーや工務店以外で、設計事務所で建てたいという方が居たとしても、どうしても設計・監理に対する金額が独り歩きして、「設計事務所は高い」「敷居が高い」といった印象操作がされているのが現状です。
設計事務所によってお客様にご提示する報酬は異なりますが、殆どが告示や掛かる人件費(人工)に基づいた根拠ある数字です。
「高いイメージ」の理由
適正報酬という概念がなく、「設計料は本体に含まれている」「図面だけなのに高すぎる」といったイメージが独り歩きして、建築士の報酬は安い・高い言われていると考えます。
結論として建築士の給料は安くありません、かといって高くもありません。
設計内容・設計期間等に応じた適正な金額をお客様から頂いているのです。
ブラックジャックのような法外な設計料を設定している建築家は恐らくいないでしょうし、設計料を値切られたり、低く設定すると、お客様・設計者の双方に一つもいいことはありません。
【理由4】誰でも設計ができてしまうから

「設計」とは、建築士法第二条4項にて、以下のように定義されています。
「設計」とはその者の責任において設計図書を作成することをいう
また「設計図書」とは、建築基準法第二条の1項九の三号にて以下のように定義されています。
建築物、その敷地又は第八十八条第1項から第3項までに規定する工作物に関する工事用の図面(現寸図その他これに類するものを除く及び仕様書をいう)
つまり、法律で定義された、責任があるものです。
私は、建築士資格を責任とせず、名義を借りることによって誰でも設計できてしまっていることが問題があると思います。

住宅規模程度の建物であれば、構造や設備は住宅設計の経験者又は施工経験者の意見を借りれば設計できてしまいます(本当は住宅の構造や設備はとても奥深いものです)
よって、建築士の資格や建築士事務所としての登録がなくても、お客様から仕事を受け、設計事務所に法的な必要がある箇所は丸投げをし、自分が設計しているかのように設計者を名乗る者が多いのです。
しかし、委託される設計事務所が責任を持って、建築主に会い、設計内容や重要事項を説明し、きちんと設計業務委託契約を結んでいれば別です。
これは名義貸しにはなりません。
お客様に建築主と建築士のパイプ役として折衝する、設計やデザインを監修するコンサルティング業務にあたります。

つまり、正規の建築士ではないのに、設計のような業務を受け、責任の下に正規な報酬を要求していないことが問題(報酬が高いか安いかは別問題として)であり、それが建築士の地位を落し、「設計」って別にそんなに大変なことじゃないよね、という意識が一般に広がっているようにも思えます。
もちろん、「設計」が多くの方々に近い存在になることはとてもいいことです。現在では安価なPCソフトで、簡単に間取りや住宅のデザインを考えることができます。
しかしこのような仕事を「設計」の業として、資格がないのにお客様から報酬を得て、名義を借りている現状は、建築士としては少し違うのではないかなあと思います。

建築士で稼ぎたいなら一級建築士は必須資格
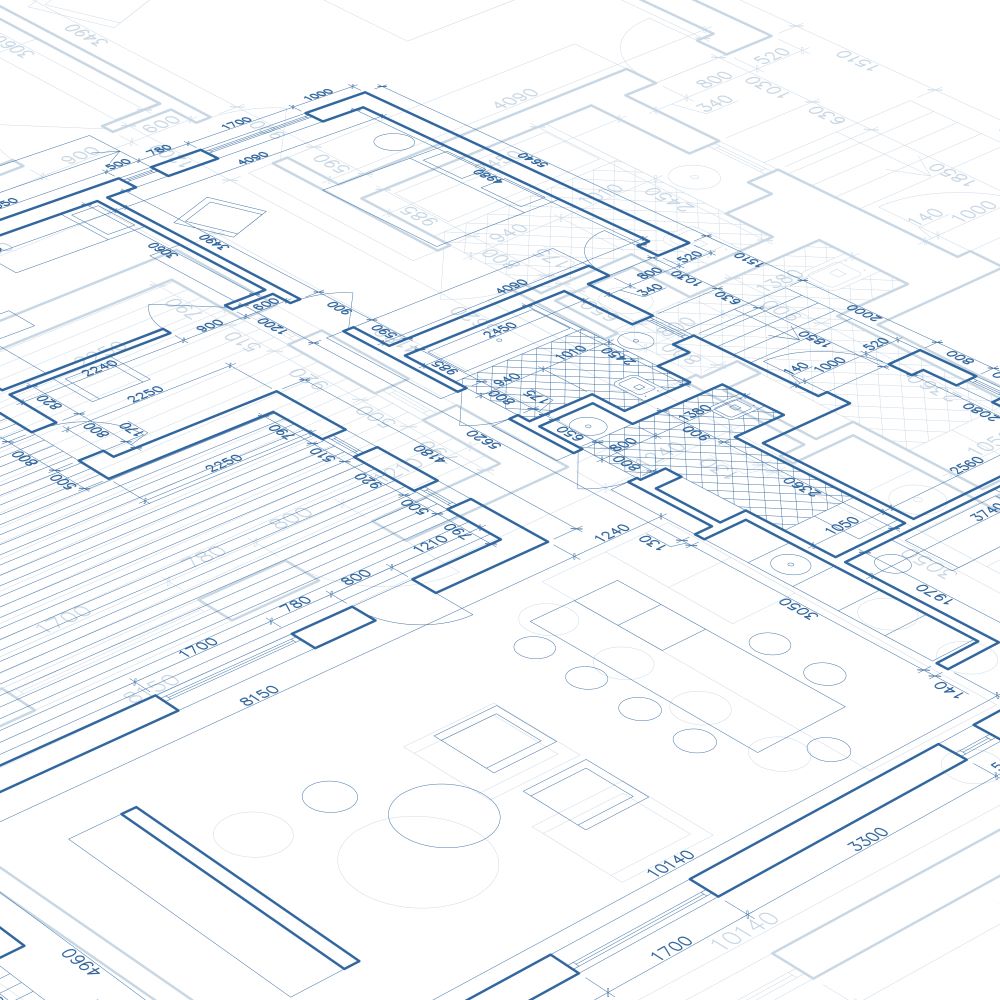

設計や監理、工事管理の現場でも、建築士に求められる社会的なニーズは大きく多様化してきています。
一級建築士は、二級建築士や木造建築士と比べ、より多い知識と経験が必要とされます。
社会的な責任や期待が多いのですが、その分、対価としての報酬も多いです。
資格が無くても、会社に属していれば仕事はできます。
仕事ができる方はたくさんいます。
しかし、資格があるに越したことはないですよね。
より上位の建築士を目指す方は、以下の通信講座又は受験対策講座をオススメします。
スタディング/ https://studying.jp/
総合資格学院/ https://www.shikaku.co.jp/
日建学院/ https://www.ksknet.co.jp/nikken/index.aspx
一般社団法人 全日本建築士会/ https://ssl.kenchikukouza.org/index.html
建築士が年収1,000万円を超えることは可能?


結論から言うと、可能です(私自身の経験談をベースに記載させていただきます)
私自身も、多くの同業者(設計事務所、工務店、建材メーカー、ゼネコン)の方とお会いして年収について話すこともありますが、1,000万円以上の所得の方も本当に多いです。
【1】大手組織設計・スーパーゼネコンに所属する
設計事務所でいうと、日建設計、NTTファシリティーズ、三菱地所設計、日本設計、JR東日本建築設計等の設計事務所売上高上位の組織設計事務所に、年収1000万円以上の建築士が居られました。
詳しい具体的な年収についてはなかなか明かされませんが、個人設計事務所よりは大手組織設計事務所(特に売上高上位20位以内)、スーパーゼネコンの設計部等では高所得を望めると思います。
しかし、上記の大手組織設計事務所やスーパーゼネコンに属することは、並大抵ではありません。
求められること
新卒であれば、学歴やポートフォリオの完成度(将来性)等を要求され、転職であれば、様々な用途・構造・規模の設計経験等が求められます。
【2】独立して年間5棟以上元請けの設計・監理業務を受注する

まず、独立して元請けの仕事を頂く(自分の看板で仕事を受注する)ことは、非常に非常に大変です。
何百万、何千万のお金の使い道を任せていただくことと同じことですし、失敗は絶対に赦されませんので、「信頼」を得ることなく受注は不可能です。
仮に住宅(木造2階 50坪 施工費3000万円程度)の設計・監理を受注する事を想定すると、設計・監理料は150~250万円程度でしょうか。
単純に4棟受注すれば売り上げは1,000万円ですが、人件費や通信費等の諸経費は必ず発生しますし、一人で4棟はギリギリしんどいラインです。

それでも、スタッフ一人に年間で300万の人件費等が掛かるとすると、5棟受注してもなかなか1000万円には辿り就きにくいかもしれません。
そうなると設計・監理の質と量を法定内で上げ下げし、利益をコントロールする必要がありますよね。
安定している設計事務所は少ない
しかし、設計・監理一本で高所得を得て、経営が安定している設計事務所はなかなかなく、CG・模型・提案書制作、確認申請や省エネ計算の代行等を行い、所得を増やしている事業所も多いのではないでしょうか。
【3】集合住宅系の営業設計職に就く
前提として、集合住宅を商品としている営業設計(営業)はとてもハードで大変です。
顧客訪問からノンアポ訪問(訪問の約束をせずに飛び込みで営業に伺う)まで、会社によってことなりますが、いずれの場合でも、受注した場合の歩合は大きいです。
若くして、月収200万円や年収1000万円を超えることも可能だと思います。
営業設計職として、建築士の資格を所有していると、専門知識に精通していることに加えて、社会的な信頼度も上がるため、よりお客様のハートをつかみやすくなるのではないでしょうか。
生涯年収で見たときの建築士の給料


令和元年賃金構造基本統計調査によれば、一級建築士(男性)の所定内給与額(全国平均)は約42.0万円/月であり、賞与は約150.0万円というデータが算出されています。
このデータを参考に、生涯年収で見たときの建築士の給料をその他の国家資格と比較してみましょう(※一級建築士の給与額は男性のみの記載となっています)
勤続年数を22歳から65歳までの43年と仮定すると、生涯年収は(42x12+150)x43≒2.81億円となります
同条件で、所定内給与額と賞与を職業別に変えて算定すると以下の通りになります。
| 一級建築士(男) | 約2.81億円 |
| 歯科医師(男) | 約2.72億円 |
| 弁護士(男) | 約3.13億円 |
| 公認会計士(男) | 約2.98億円 |
| 医師(男) | 約4.67億円 |
難関とされる国家資格の中でも、一級建築士の生涯年収は引けを取らない額となっています。
勤続年数で、上記の職業において比較すると以下の通りになります。
| 一級建築士(男) | 約14.2年 |
| 歯科医師(男) | 約5.4年 |
| 弁護士(男) | 約5.0年 |
| 公認会計士(男) | 約10.5年 |
| 医師(男) | 約5.5年 |
あくまでデータ上での話となりますが、比較的長い勤続年数となっています。
恐らくですが、プロジェクトが2~3年と長いため、他の職業と比べて転職のタイミングが難しいこともあるのかもしれません。
一級建築士に合格するためには


学科と製図試験の両方をパスすための学習時間は約2,000時間必要です。
詳細は、一級建築士の難易度は?の記事を参考にしてみてください。
非常に根気と受験のテクニックが必要な資格でもあります。
資格受験生のほとんどが、仕事をしながらの挑戦となり、膨大な学習時間が必要となってくることから、仕事と学習、家庭と学習のバランスの維持が困難といえます。
そこで、効率的に学習するために、以下の通信講座又は受験対策講座をオススメします(★の評価は、あくまで個人的な意見です)
【1】スタディング

学科・製図講座とも、動画講義となります(学科+製図費用は約9.8万円+税)
スマホやタブレット等のITを活用した、机に座らなくても勉強できる新しい学習スタイルの講座です。
仕事で忙しくて時間がない方にも隙間時間でいつでもどこでも学習できる、あたらしい学習スタイルです。
【スタディング】のポイント
特に、試験対策に特化し「最短で試験に合格するために考え抜いた講義」を掲げ、必要最小限の労力で効率的に合格に必要な知識が学べるテキストとなっています。
| 料金 | 学科+製図:約9.8万円+税 |
| 内容の充実度 | ★★★★☆ |
| 口コミ | ★★★★☆ |
| サポート体制 | ★★★☆☆ |
| 合格率 | ★★★★☆ |
【2】総合資格学院

建築士資格の最大手のスクールです。
業界合格率1位として宣伝されています。
学科講座・製図講座共に、講師が解説するライブ講義であり、緊張感と臨場感があります。
テキストはとても充実しており、過年度の問題から新傾向まで網羅しています。
【総合資格学院】のポイント
一番のポイントは、全てプロの講師によるライブ講義であるということです。これは他社にないオリジナルであり、試験にでるポイント、解法などを分かりやすく教えてもらえます。
講師は実務のプロであると同時に、指導のプロでもあります。
定期的に開催される社内研修より、指導カリキュラムとノウハウを全国で共有し、指導方法を統一できるため、講師の指導力が非常に質が高いとの評判があります。
受講生へのフォローも充実しており、社員と講師が受講生の成績を綿密に分析し、各々に合った学習方法を提案しています。
受講費用はかかりますが、最短最速で資格をとりきるという観点で、個人的には一番オススメです。
| 料金 | 学科:約73.5万+税 製図:約48万円+税 |
| 内容の充実度 | ★★★★★ |
| 口コミ | ★★★★☆ |
| サポート体制 | ★★★★★ |
| 合格率 | ★★★★☆ |
【3】日建学院

建築士資格の大手のスクールです。

学科講座は、基本的には動画となります。
製図講座は、講師が解説するライブ講義となります。
【日建学院】のポイント
合格率の高い映像学習にこだわりを置いていて、CGやアニメーションを盛り込みながら分かりやすさを追求した講義となっています。
| 料金 | 学科:約65万+税 製図:約45万円+税 |
| 内容の充実度 | ★★★★☆ |
| 口コミ | ★★★★☆ |
| サポート体制 | ★★★☆☆ |
| 合格率 | ★★★★☆ |
【4】一般社団法人 全日本建築士会

学科・製図講座とも、ライブ講義となります。
【全日本建築士会】のポイント
大きなポイントとしては、講座費用が安く少人数ごとのライブ講座のため講師と受講生の距離が近く、コミュニケーションを取りやすいことが挙げられます。
また、出席率80%、模擬テスト80%以上の受講生で万が一不合格になってしまわれた方は、翌年度に限り受講においては無償とされています(テキストは有償)
| 料金 | 学科:約19.2万+税 製図:約17.9万円+税 |
| 内容の充実度 | ★★★★☆ |
| 口コミ | ★★☆☆☆ |
| サポート体制 | ★★☆☆☆ |
| 合格率 | ★★★☆☆ |
【5】TAC

学科講座は、動画講義となります。
製図講座は、講師が解説するライブ講義となります。
講座のテキストの内容は資格学校の大手と引けをとらないぐらい充実しています。
【TAC】のポイント
大きなポイントとしては、講座費用が大手の約半額であり、受講費用の負担が軽減できるという点です。
TACの合格者の声を調べてみると、通学できない場合でもWEB講義や質問メールなどでのフォローアップも充実しており、学科・製図共に受講者の満足度が高いスクールとなっています。
| 料金 | 学科:約34万+税 製図:約22.5万円+税 |
| 内容の充実度 | ★★☆☆☆ |
| 口コミ | ★★★★☆ |
| サポート体制 | ★★☆☆☆ |
| 合格率 | ★★★☆☆ |
まとめ

今回は、建築士の給与について述べさせていただきましたが、一級建築士を取得すると設計の幅も広がり、仕事の選択肢も増えてきます。
建築士という仕事は、プロセスと結果が必ずしも結びつく仕事ではありません。

センスの良し悪しで片付く仕事ではありませんし、建築の中で「センス」という言葉はあまり適切ではありません。
どれだけ真面目に、そしてストイックに建築に向き合ったかが、多くの人々を感動させる建物を設計できる糧になると私は考えます。
よって、若いうちに建築士で高収入を得たいという考えている方は、地道にステップアップして収入を増やすべきだという考え方にシフトチェンジしましょう。

どうしても勉強に費やす時間は、実務に負担が掛かってきます。
仕事に負荷が掛かりにくい若手の時に、一気に苦労して取得しておく方が、絶対「楽」だと思います。
法改正により、今年から多くの若い受験生が一級建築士を目指します。
その分、競争率も激しくなります。
お金も精神力も体力も使う建築士試験は1年で終わらせましょう。
早く効率的に取得して、建築士としてのキャリアを長く築きましょう!
石橋優介(一級建築士)
最新記事 by 石橋優介(一級建築士) (全て見る)
- 【1,000万円は可能?】建築士の給料は安い?独立開業した一級建築士が解説! - 2020年7月7日
- 一級建築士の難易度は?現役資格学校講師が教える合格の勉強時間の目安や最短合格法!! - 2020年6月16日
- 建築士の受験資格を通信で取得!建築士が教える最短ルートはコレ - 2020年5月25日
